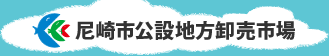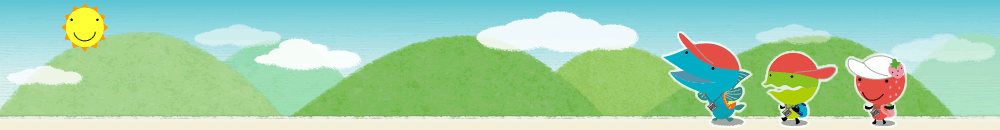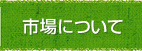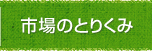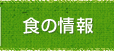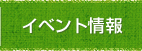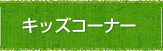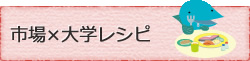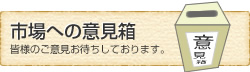2014年7月の食材
2014年7月の食材【ハモ(鱧)】

夏の関西を彩る京都の祇園祭りや大阪の天神祭りは有名ですが、その時期によく料理に出てくるのが"鱧"を使った「鱧料理」です。
昔、海から離れた京都まで生きた魚を輸送する技術がない頃、唯一生きた状態で輸送できた魚が生命力の強い鱧でした。しかし、小骨が多く料理をするのが大変な魚で、海沿いでは昔から食べられてきたものの、料理のわずらわしさから、家庭では食べにくい魚でしたが、京都の料理人が料理技術を磨き京料理に出されるようになりました。
また、最近では、骨切を機械で処理できるようになり、スーパーの陳列台にもたくさん並ぶようになりました。
鱧の身は、蒲鉾(鱧板、鱧竹輪)の原料としても使われるほか、大型サイズの皮は、醤油をつけて焼き上げる「ハモ皮」も好まれており、捨てるところの少ない魚です。
活魚と、野締めでは価値や料理方法にいろいろと差が出るので、生きたままの搬入が多い魚ですが、この魚は肉食の獰猛(どうもう)な魚で、"食(は)む"、"咬(か)む"が名前の由来になるくらい、気性が荒く、これに咬みつかれると腕の肉が食いちぎられるぐらい危険な魚です。
主産地
暖海性の魚で、本州は福島以南の太平洋岸や瀬戸内海、東シナ海、黄海、などに分布しています。関西には、瀬戸内海沿岸各地に生息しており、近海物では淡路の沼島産などが有名ですが、輸入品では韓国、中国から入荷があり特に韓国からの活魚が高値で取引されています。
旬は2回、”梅雨の水を飲んで育つ”といわれる、6月~7月ごろの夏鱧、もうひとつは8月ごろ産卵を終えて、脂が乗り始めた”金ハモ”、”松茸ハモ”、”名残ハモ”など言われる晩秋から初冬のころのハモです。
選び方
1匹まるごとのときは、目が透きとおり、体表が薄いべっこう色で、表面の粘液(ぬるぬる)が透明なものを選びましょう。
切身(骨切した切身)の時は、できれば活け締めか野締めの確認をしてください。白身の淡白な魚なので、湯引きなど淡白な料理の時は血なまぐささの少ない活け締めを選び、フライ等の時は野締めでも良いですが、鱧を楽しむにはやはり活け締めがお勧めです!
料理法、食べ方
ハモを食べるためには、まずは骨切が必要です。プロは1寸に26筋の包丁を細かく入れて骨きりをしますが、素人には難しいので骨切りしたハモを選びましょう。
骨切したハモを、湯引き(落とし)、照り焼き、フライ、すき焼きなどにして食べるのが一般的だと思われます。
淡路島出身の方から教わった料理ですが、お勧めは、すき焼きで、骨切りした鮮度のいいハモと、淡路産の玉ねぎ、三つ葉だけのシンプルな食材を割り下(割り下にはハモの骨からだしをとって)で煮込んで食べます。あっさりコクのある味で、病み付きになります。くれぐれも、ハモの鮮度はいいものを選びましょう。鮮度が命です。
また、ハモ皮を焼いたものを細かく刻んで、きゅうりをもんだものをあわせたハモざくざく(はもきゅう)などもさっぱりとして美味しいです。
鱧皮は、できたら皮の厚いものがおいしいのでお勧めです。
また、ハモの身は蒲鉾の原料に使用されます。その原料の殆どが海外生産の輸入品なのですが、関西には以西物などの生のハモを使用して蒲鉾を作る業者さんが何件か残っています。鱧板(焼板)1枚、数千円もしますが、味は良く、当然鱧皮も製造しているはずです。鱧本体もお勧めですが、もし機会があれば加工品も一度試してみてください。
仲買の目利き、おすすめ
ハモの季節を迎えて、店の水槽にもハモがたくさん泳いでいます。
やっぱり、ハモは生きているのが最高なので、一度当店にもお立ち寄りくださいね。
私がこの仕事をしていて、一番うまいと思ったハモは、高知は四万十川の河口周辺で漁獲されたものでした。(河口なので砂地で、四万十川の豊富な魚に支えられて、飽食なためでしょうか。)
残念ながら、今は尼崎への入荷はないのですが、機会があったらもう一度取り扱いたいですね。
できたら、取り扱いつつゆくゆくは尼崎の名物にできれば最高なのですが。
協力:尼崎水産物卸協同組合 ㈱浜光水産
2014年7月の食材【キハダマグロ(黄肌鮪)】

キハダマグロという名前ですが、黄色いのは体側線上の一部と背びれ、尻ひれのふちだけで、英名は"Yellowfin tuna"なのです。
本当は黄鰭(キビレ)マグロが正解のような気がしますが・・・・もし解体ショーなどで1匹丸ごとを見る機会があれば、見てみてください。
関西ではメジャーなマグロで、一般的に店で出てくるマグロはこのマグロでしょう。ちなみに関東ではメバチマグロやクロマグロが多いです。
赤道直下の熱帯域が主な生息地で、クロマグロのような長い距離の回遊をしないことから、身の赤みが他のマグロに比べて薄く、尻尾の方の身になると白いはっきりとした筋が入るのが特徴です。
また、体温を維持するための奇網(きもう)もほかのマグロより発達していないため、脂肪分の少ない赤身になっているようです。
生キハダマグロの旬は夏で、桃色の身が特徴で、夏のマグロとも言われています。
主産地
太平洋、インド洋、大西洋の暖海や熱帯地域に広く分布していますが、地中海には生息しません。日本の各地沿岸にも夏に回遊します。
水温18~31度の海の表層~中層に生息し、イルカの群れやカツオの群れについて回遊したり、島や岩礁帯に瀬付き群となったりします。
赤道中心に北緯40度から南緯40度の範囲で主に延縄漁で漁獲され、冷凍や生の空輸品として日本に入ってきます。
日本でも高知、南紀勝浦、九州、沖縄から入荷があります。
選び方
切身(柵(サク))の状態での販売が多いと思われますが、身に張りがあり、薄い赤色で、透明感のある身が良いでしょう。また、身には筋がありますが、その状態で簡単に見分ける方法があります。その方法は、サクを長い方を横向きに置き、①筋目が平行に入っている、幅が広いものはとても良質。②斜めに入っているものは並品。③年輪風に入っているはあまり良くない身質ですので、できるだけ①または②を選びましょう。
料理法、食べ方
なんといっても刺身でしょう。脂肪が少なく、食べやすい身質です。
とろろをのせた山かけや、醤油と味りんで作ったタレにつけた漬けや、酢味噌和え、カルパッチョなどもお勧めです。
逆に、照り焼きやネギマなどは、脂肪分が少ないのであまり向いていないと言われます。
また、缶詰のツナ缶のように、調味料や油分を足してやると、別の食感や味が楽しめます。
仲買の目利き、おすすめ
キハダマグロは、基本的にはあっさりとした赤身のマグロです。だからいくらでも食べれますよ!
当店では、赤々とした赤黒系の身が、お寿司屋さんなど業務筋へは売れ筋になります。
ちなみに、私はもちもちとした脂の乗った食感の身が好みです。このような身は包丁で切り分けるとき、身が包丁にまとわりついてくるんですよ。
マグロ全般に言えることですが、生息場所(水揚地)や冷凍、生鮮などの保存、運搬方法のほか、大きさ、身の部位によって条件が変わると味や食感が大きく変わってくる魚でも有ります。
マグロは奥が深い魚です。人それぞれ好みは違いますが、自分にとっての一番のマグロを探しにぜひ「市場開放フェア」にお越しいただき、貴方にとって一番のマグロを探しにきて見ませんか?
皆様のご来場をお待ちしています!
協力:尼崎水産物卸協同組合
(有)金井商店 金井 英人・祐子さん