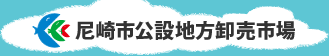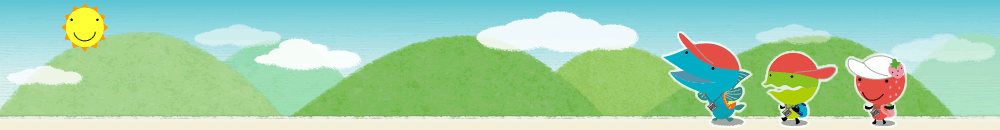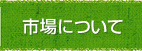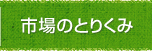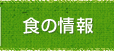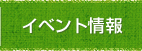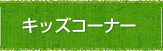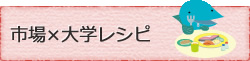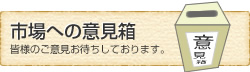2014年9月の食材
2014年9月の食材【スルメイカ(鯣烏賊)】

「スルメイカ」は、軟体動物門頭足網ツツイカ目アカイカ科に属しています。イカの種類は非常に多く、世界の海では約500種、日本近海では130種ほどが知られています。日本で食用として漁獲されているのは20種ほどですが、その内で一番多く漁獲されているのがスルメイカです。体長(胴の長さ)は30cm前後まで成長し、寿命はふ化してから産卵までの1年で、産卵が済むと死んでしまいます。日本近海での生息地は、千島列島付近からの日本沿岸各地、朝鮮半島周辺、東シナ海に分布しています。日本でも九州から北海道の沿岸で漁獲され、春先九州で始まった漁は夏に向けて北海道まで北上し、夏の終わりに反転して山陰沖周辺で終漁を迎えます。
群(むれ)は大きく分けて3つの季節群があり、「秋季発生群」といわれる九州西方面で生まれ、日本海沖合で大きくなる群と、「冬季発生群」といわれる東シナ海で生まれ、黒潮に乗って三陸や北海道沖まで北上する、資源量、回遊距離とも一番大きい群、また、「夏季発生群」といわれる日本海中部から九州西岸で梅雨時から夏ごろに生まれて隠岐から能登半島周辺に分布する小型サイズの群の3種類に分けられ、春先から年末にかけて主に漁獲があります。もともとスルメとはイカを干したものの意味でしたが、この種類が一番適していることから、「スルメイカ」の名前がつきました。正式名称は「スルメイカ」ですが、「マイカ」と呼ばれることもよくあります。ただし、イカの地方名は、その地方で一番獲れるイカを「マイカ」と呼ぶところもあり、地方によっては「マイカ=スルメイカ」ではない所もあります。
世界のイカ類の漁獲の4割を日本が消費しているといわれ、日本産だけでも100万トン近くの漁獲量(日本全体の漁獲の5%)がある重要な魚種となっています。
イカ類の食品成分の特徴は、低カロリーで良質のタンパク質や脂肪を含み、動脈硬化の抑制、肝機能増強、眼精疲労の回復などの作用があるDHA・EPAや、コレステロールを下げる効果のあるタウリンなど、栄養成分が多く含まれています。
主産地及び旬
主な産地は、北海道・青森県・宮城県・石川県・岩手県など。
旬は5月から9月頃。
選び方
新鮮なものは、体色が茶色や黒色をしていますが、時間がたつと白くなり、その後は赤茶色に変化してきます。目も最初は澄んでいて、飛び出しているように見えますが、時間がたつと白く濁ってきて、飛び出しもなくなってきます。身に張りがあり、体色が茶色や黒色で、目が澄んでいて飛び出しているものを選ぶと良いでしょう。
料理法、食べ方
刺身、炒め物、フライ、いか飯、ボイル、丸焼き、煮物、一夜干しなど色々な料理に使えます。
新鮮なものは、歯ごたえが楽しめる刺身で。また、加熱調理をすると甘みも出るので違った美味しさを楽しむことができます。
成長が早い分、多少水っぽい身質なので、一夜干しなどで水分を適度に取り除いて調理すると旨味が分かりやすくなります。また、塩辛や干し物(スルメ)などの加工品もお勧めです。
なお、いか類は、水で洗ったり、直接氷に触れると味が極端に落ちます。水で洗うときは、解体するときだけにして、皮をむいたらなるべく水に触れないようにしましょう。
仲買の目利き、おすすめ
今年のスルメイカは、春先の水温が低かったためイカの成長が遅れ、なかなか売れ筋サイズの入荷がなくヤキモキさせられました。8月に入り順調に入荷しだしたと思ったら台風の影響で入荷無し・・・と、天然の魚は難しいですね。
刺身で食べると、剣先いかや甲いかに比べて旨味がいまひとつ薄いのですが、加熱すると甘みも増しておいしいイカです。
大型サイズ(300g~)になると、身が固くなってきますので、柔らかい食感が好きな方は小型サイズを選び、噛み応えのある食感が好きな方は大型サイズを選ぶと色々な食感が楽しめますよ。
冷凍スルメイカも美味しいですが、生で鮮度の良いイカは更に美味しいので、是非お試しくださいね!
協力:尼崎水産物卸協同組合
森本水産㈱ 北 昌樹さん
2014年9月の食材【サンマ(秋刀魚)】

サンマはダツ目サンマ科の回遊魚で北部太平洋と日本海に分布しています。体長は35センチ前後まで成長し、体型は細長く、尾びれ・背びれが後方にあり、口はややくちばし状になっています。秋から春先にかけて産卵し、稚魚は黒潮の流れの周辺の暖かい場所で越冬し、春から夏にかけて主食である小型の甲殻類、オキアミなどの餌が豊富な北海道~千島沖に回遊します。夏の盛りに、太平洋各地に散らばっていたサンマは千島沖に集結し、8月下旬ごろから産卵のため南下を開始します。
100%天然魚で国産の魚と問われると、数少ない候補に上がる魚ですが、近年はロシア公海で漁獲されたサンマが加工用に輸入されているため100%ではなくなってしまいました。8月の解禁とともに新物が店頭に並びだすと、夏から秋への季節の変わり目を感じる方も多いと思います。
現在の「秋刀魚」という漢字が使われるようになったのは大正に入ってからで、それまでは「三馬」という字が使われていたようです。築地では、三馬を略して「午(うま)」という符牒(ふちょう)で呼ぶこともあるそうです。もともとは細長い体つきから、「狭真魚(さまな)」と言われていたのが、サンマに変化したそうです。
さんまの流通は一汐した塩蔵品が主体でしたが、最近では、流通の高度化により鮮魚流通が活発となり、以前は浜でしか食べられなかった刺身などの生食物が、関西でもスーパーマーケットなどで見かけるようになりました。栄養価では、イワシ、サバに次いでDHAやEPAが多く含有されており、ビタミンE、A、B12なども豊富に含まれています。
サンマの塩焼きに、ビタミンCを含むレモンやスダチ、大根おろしを添えれば、たいへん栄養価の高いおかずになるのです。
主産地
主な産地は、北海道から宮城県・福島県・岩手県・千葉県など。
選び方
生の場合は、皮の張りが良く、ピカピカのものを選びましょう。
口ばし部分の黄色やオレンジ色がはっきりと出ていて、頭の後ろの魚体が大きいものは、脂のりが良いとされています。冷凍になれば、どうしても皮の張りが失われてしまいますが、口ばしや魚体の選び方は同じです。
料理法、食べ方
塩焼きが主流ですが、刺身、煮付け、揚げ物、味醂干し、丸干し、酢締めなど色々な料理で美味しく食べられます。
鮮度のいいものは、一度刺身で食べてみてください。濃厚な脂の旨味とねっとりとした食感が楽しめます。
仲買の目利き、おすすめ
水温の影響と言われていますが、今年のサンマはなかなか北海道に近寄ってくれなかった為、8月の解禁後、なかなかまとまった入荷がありませんでした。盆明け以降からやっと入荷がまとまりはじめ、価格も下がってきました。
サンマはやっぱり、塩焼きが一番旨いのですが、お勧めはタタキです。アジなどと同じように3枚におろして皮・骨を取り除いた身にネギやしょうがの薬味を加えてタタキにして、食べてみてください。サンマはアジなどと比べて脂のりがいいので、また違った味を楽しめますよ。
これからシーズン本番を迎えるサンマを、ぜひ食卓にご活用ください!
協力:尼崎水産物卸協同組合
森本水産㈱ 北 昌樹さん