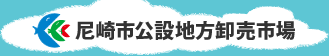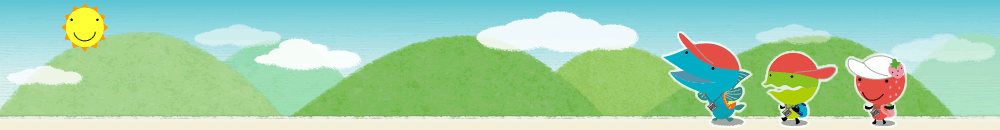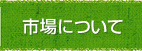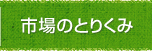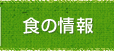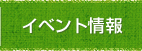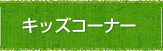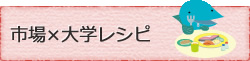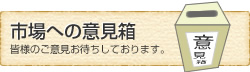2014年10月の食材
2014年10月の食材【いくら】

"イクラ"とはロシア語で魚の卵を指します。日本で主に食べられている"イクラ"は白鮭の卵巣が一番多く、輸入品の紅鮭の卵巣やマスの卵巣も中には含まれます。日本で言う"イクラ"は、主に白鮭の成熟卵の卵巣膜を破り、中の卵をバラバラにして塩漬けにしたものを指します。しかし"イクラ"は上記の通り、いろいろな意味で言われますので、中身を確認しないと思ったものと違うなんてこともあるかもしれません。また、良く似たもので、未成熟卵をそのまま塩漬けにした"筋子"や、バラバラにした卵を醤油や味醂、酒の中につけた"いくらのしょうゆ漬け"などがあります。8月末ごろから北海道で順次定置網漁が解禁され、それとともに北海道から入荷が始まり、11月にかけて、北海道~東北へとだんだん産地が南下してくるのが特徴です。輸入品の紅鮭やマスの卵巣は、夏前に漁獲され、現地で塩漬けやしょうゆ漬けに加工され、日本に一部輸入されます。ちなみに海外では、塩漬けのイクラが食べられてるようですが、日本食ブームの影響で、しょうゆ漬けなども一部出回っているようです。
主産地
白鮭は日本の太平洋側は利根川から北、日本海側は山口県以北の河川に産卵のため遡上(そじょう)します。海外では、朝鮮半島からシベリアのレナ川、東部太平洋ではカリフォルニア州からカナダ沿岸に生息しています。川で産卵、孵化した稚魚はやがて川を下り、北太平洋、北極海を索餌(さくじ)回遊し、生まれた川に産卵のため戻ってきますが、川の周辺に設置された定置網で漁獲され、中の卵巣が抜かれて箱詰めされ、発送されます。なお、白鮭が川に入ると、卵の表面が産卵に備えて堅くなり、ピンポン玉のようになるそうで、とても食べられた代物ではないそうです。後述する、「料理法、食べ方」であるように、ほぐすときに使う水の温度を上げると同様の現象が起きますが、やっぱり堅くなってしまうので旨くないです。
選び方
店頭で選ぶ際は、卵の色が鮮やかなオレンジ色で、粒がそろっていて大き目のものを選ぶと良いでしょう。後述する料理法のように、ご自宅でしょうゆ漬けにするのをお勧めしますが、必ず当日中に加工してしまいましょう。時間がたつと、卵の鮮度が落ちて、ばらすときのロスが多くなる為、せっかく買ったイクラが台無しになります。とりあえず、鮮度が一番、粒の大きさが2番です。しょうゆ漬けする際はたれを先に用意して、冷蔵庫で冷やしておいてから買出し、加工するとスムーズに進みます。
料理法、食べ方
いくらのしょうゆ漬けがベストです。
用意するもの:いくら、ボウル、出来れば新品のステンレス製の焼き網、ザル、醤油、味醂、酒、ザラメ、出来上がりを冷蔵保管するタッパー
1.最初にたれを作っておきます。味醂と酒を鍋に入れて煮立てて、アルコール分を飛ばします。お好みでザラメを入れて、醤油を加えます。これを冷ましてタッパーに入れておます。割合は味醂:酒:しょうゆが3:2:1とザラメが0.5ぐらいにすると甘めに仕上がります。1kgのイクラで400ccも有れば漬かります。配合比はお好みで調整してください。この配合比ですと、やや甘めに仕上がります。いくら丼にするときは甘めのほうが食べやすいかと思われますが、試食して決めましょう。
2.筋子を買ってきて、卵巣膜を破り、ザルの上に焼き網を乗せ、卵を軽く押し付けながら網の上を滑らせ、卵をバラバラにします。このとき、力加減に注意しましょう。乱暴に行うと食べる分がどんどん減ります。ぬるま湯(40℃程度)に少し漬けてからほぐすとほぐしやすくなりますが食感が堅くなります。軽快なプチプチ感を求めるなら、地道にほぐすことをお勧めします。
3.ほぐし終わったら、ボウルに入れて、食塩を少し入れながら水を注ぎ、白濁した卵の膜や、血管などを何回か水換えしながら掃除します。ここで、水を切ってはごみをしっかり取り除きましょう。血管が残ると生臭くなります。また、塩分はしっかりと取り除かないと、しょうゆ漬けが塩辛くなります。
4.ざるに入れたまま水切りしながら冷蔵庫で1時間くらい寝かせます。
5.水切りしたイクラをたれに漬けて冷蔵保管します。3時間も漬けると食べられるでしょう。アルコールの残り具合で保管期間は変わりますが、1週間程度は冷蔵保管できます。冷凍するときは、一度たれをきってから密閉容器に入れ、冷凍するとしばらく保存出来ます。
ぜひ、ご家庭でいくらのしょうゆ漬けを作り、炊き立てのご飯にたっぷりと乗せて、いくら丼を堪能しましょう!!
仲買の目利き、おすすめ
今年は、8月の末から順調に入荷が始まり、ほぼ毎日入荷がある状況です。9月に入り、粒も大きくなってきて、価格も平年並みかそれ以下の安値で推移しています。ここ数年、いろいろな要因があり、高くて手が出しにくい価格が続きましたが、今年はお求め易い価格で販売しております。ぜひ、店頭で見つけて、しょうゆ漬け等に加工して秋の味覚を堪能してください。
協力:尼崎水産物卸協同組合
十代水産 十代 佳子さん
2014年10月の食材【 かつお(鰹)】

"青葉鰹に桜鯛"、"猫に鰹節"など、ことわざにも使われるメジャーな魚で、石器時代の貝塚などからも骨が出てくるぐらい、昔から食べられている魚です。鮮度の低下が早い為、加熱したり、鰹節などに加工しての流通が殆どで、江戸時代ごろから次第に生食も始まったようです。鰹の名前の由来は、大量に獲れる魚を指す"カド、カツ"や食料を指す"カテ"が語源といわれ、その後、鰹節や干した物が都などで流通するとき堅い魚、つまり堅魚が訛ってカツオとなり、今の鰹という字が当てられたそうです。サバ科カツオ属に分類され、カツオ属はカツオ1種だけで、仲間にはソウダガツオ属のヒラソウダ、マルソウダが、あとハガツオがいます。最近では、カツオを原料にした油漬缶詰や水煮缶詰が世界各地で売れていて、東南アジアや南方海域で旋網(まきあみ)などによる大量に漁獲されるようになり日本沿岸の資源量が大幅に減少しているようです。
主産地
全世界の暖かい海に分布しますが、日本近海では、北海道以南を回遊し、日本海にはほとんど分布しません。理由は、夏場に中国の黄海などから流れる淡水交じりの海水を嫌うからだそうです。日本近海の鰹は、黒潮に乗って南方から北上してきて、夏ごろには北海道の近くまで北上し、9月以降水温が下がりだすと今度は南に向かって南下します。北上の時は沿岸域を泳ぐこともありますが、南下の時は沖合の中層を泳ぎます。産卵期は夏と冬で、赤道周辺では年中行われているようです。2歳魚は上記のような大きな回遊を行うが、3歳魚は小笠原や南西諸島周辺までしか北上せず、4歳魚以降は太平洋の真ん中に集まるそうです。日本近海で漁獲されるのは、2~3歳魚が主体となります。
選び方
一尾の状態では、表面の銀色が鮮やかで、丸々と身が張ったものを選ぶと良いでしょう。切身は、身の色が澄みきった赤色のものを選ぶと良いでしょう。身の色が茶色っぽいものは、鮮度落ちのサインになります。たたきなど冷凍の加工品は、一本釣りで生きたまま凍結(B1)と死んでから凍結(ブライン)、旋網(PS)の3種類による漁獲の仕方に分別されますが、漁獲してから、凍結するまでの鮮度維持の状態が異なる為、冷凍でもまったく違った味になるため、お勧めは断然1本釣りで生きたまま冷凍されたものです。また、身質で餅ガツオとか(おいしい)、石ガツオ(ゴリ)(まずい)など、産地の高知などでは、鮮魚での身の食感の良し悪しもあるそうです。
料理法、食べ方
身はたたき、刺身にして食べるのが一番メジャーではないでしょうか。春から夏の上り鰹は、腹側は皮がついたままの銀皮造りや、焼く代わりに表面を素揚げした揚げたたきなど、脂を他で補う食べ方がおすすめです。秋からの脂の乗った戻り鰹は、刺身やたたきで豪快に食べるのが一番おいしいです。また、塩水で茹でて、表面を乾かした生利節(なまりぶし)にして、マヨネーズをつけたり、野菜と煮物にしたりとか、切身を醤油や味醂、砂糖で甘辛く炊いて、ほぐしたものを炊き立てのご飯と混ぜたかつお飯なども、おいしいですよ。
協力:尼崎水産物卸協同組合
㈱浜光水産 多岐 篤司さん