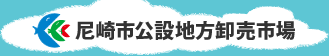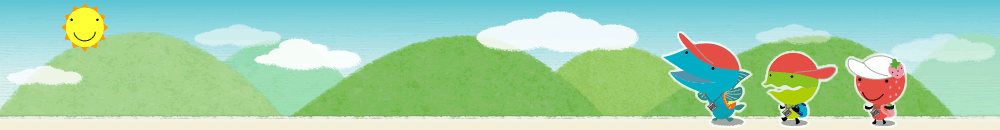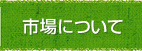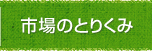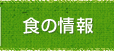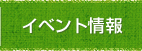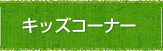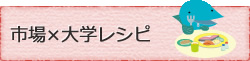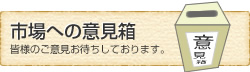2014年11月の食材
2014年11月の食材【真鯖】

主産地
全世界の亜熱帯、温帯に分布します。日本では、北海道以南の沿岸各地に生息し、季節的な南北回遊を行います。日本近海のマサバは、大きく太平洋系群、日本海系群、東シナ海系群の3つに分かれます。昼間は水深70~150mの辺りに多く、夜になると表層に浮上してきます。産卵は、東シナ海で3~6月、北海道で6~7月ごろの夜に行われ、産卵に適した水温の分布とともに産卵域も北上していきます。初夏から春にかけて、釧路沖、八戸沖、常磐沖、九州北方など、主に巻網やあぐり網、一本釣りで漁獲され、各地でブランド化も進んでいます。また一部養殖もされていて、生きたまま飲食店に卸されています(ただ、脂が多いのが難点ですが)。
選び方
1尾丸ごとの時は、目が澄んでいて盛り上がっており、丸々と太っていて、腹の部分がきれいなものを選びましょう。金色の紋が出ているものは、鮮度と脂のりがいいとされています。また、背中側の斑紋がきれいで、腹側に張りがあるものも良いでしょう。切り身の時は、背中の斑紋や腹側の部分や、皮の下にある血合肉が、赤々としてきれいなものを選びましょう。サバはマグロやカツオほどきつくはないのですが、アレルギー物質のヒスタミンが出来やすい魚でもあり、鮮度が悪いとヒスタミンが多く生成されているかもしれません。出来るだけ、鮮度のいいものを選んで、手早く調理して食べましょう。
料理法、食べ方
サバは栄養成分の不飽和脂肪酸やタウリンの含有量が多く、ビタミンB2は魚の中でもトップクラスで、鉄分も豊富に含まれてます。成分の多くは脂肪や血合肉に多く含まれており、また旨味成分の多い肉質で、味噌などの調味料との相性も抜群です。刺身やシメサバ(キズシ)、味噌煮や塩焼き、汁物や揚げ物、味醂干しなどの加工品が美味です。身の中の水分が多い為、料理の前に塩で身を締めてから調理すると、旨味を凝縮しておけます。また、地方で独特の食べ方があり、インターネットなどで調べてチャレンジするのもいいでしょう。オススメは、生のサバの切身を醤油や味醂、すりごまなどをいれたタレに漬けてご飯に乗せて食べる福岡の郷土料理“ごまさば”です。
協力:尼崎水産物卸協同組合
(株)角倉商店 角倉 克彦さん
2014年11月の食材【勢子蟹(せこがに)】

せこがにとは、ずわいがにのメスの名称のひとつで、"せいこがに"、"こうばこがに"、"こっぺがに"など産地によって名前はバラバラです。11月になると、山陰地方から石川県にかけて順次解禁され、資源保護のため1ヶ月少々の短期決戦で販売されます。昔は山陰などでは沢山漁獲があり、子どものおやつ? なんて時期もあったそうですが、乱獲などもあり現在では貴重な商品になっています。オスのズワイガニは、ロシアやアメリカ、カナダからの輸入品が多いのですが、メスのせこがには基本的には国産品です。この時期、メスは産卵のため卵を抱いており、茹でた時、甲羅の内側にあるオレンジ色の"内子"は特に美味といわれ、内臓の"かにみそ"とあえながら食べると、お酒が止まらない方も多いのでは? 山陰、石川方面からは浜でボイルした商品が主に、それ以外の産地からは生きたまま輸送されてくる場合が多いかと思われます。例年、11月の解禁日はニュースになるので、これを楽しみにされてる方も多いのではないでしょうか?
主産地
水深200m以下の深海に生息し、北はオホーツク海からベーリング海、アラスカ、北アメリカ沿岸に分布しています。日本近海では、日本海に多く特に能登半島以南から朝鮮半島東南部にかけて多く生息しています。関西周辺では、鳥取県沖から石川県沖で漁獲され、周辺の鳥取県、京都府、石川県の産地からも入荷が有りますが、兵庫県の香住、浜坂港からの入荷が多くを占めます。
選び方
ボイルしたものは、体が大きくて、外子の色がオレンジやエンジ色のプリプリしているものを選びましょう。ボイルしていても、味の劣化が早いので、当日入荷したものを当日食べきるのがポイントです。生きていても、持ち上げたとき足が下に垂れ下がり元気がないものは、できるだけ避け、良く動くものを選び、少しでも早く、茹でるか蒸し器に入れ、加熱して鮮度劣化を防ぐのがコツです。甲殻類は、死ぬと自身が持っている自己分解酵素により鮮度が落ちてしまいます。筋肉や甲羅の黒変はその自己分解酵素が働いた結果です。
料理法、食べ方
ボイルされたものは、そのまま身をほぐして食べるだけです。カニ酢やポン酢をつけて食べてもいいでしょう。外子、内子、かにみそ、肩肉が可食部で量もそこそこありますが、脚は殆ど食べるところはありません。可食部を一度取り出して、ご飯の上に乗せて食べるのもおすすめです。可食部を乗せた丼が、石川県の旅館などで出されており、当地を訪れて食した作家の開高健(かいこう・たけし)さんが絶賛し、”開高丼”という名前がついた、という話もあります。
協力:尼崎水産物卸協同組合
(株)魚熊 長岡 邦久さん