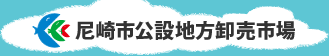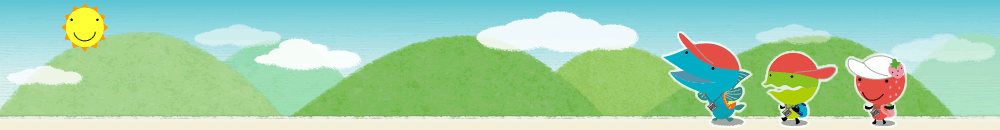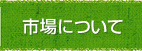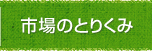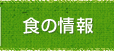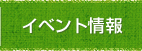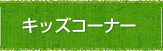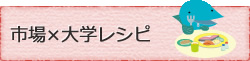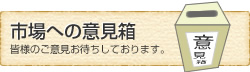2015年1月の食材
2015年1月の食材【トラフグ】

説明
毒があるのに旨い魚の代表格のふぐ、その中でも良く食べられるのがこのトラフグです。
古来、ふぐは”ふく”と呼ばれ、”布久”や”鰒”と書いてあり、平安から江戸までは”布久”、それ以降は”鰒”が用いられていたようです。
現在では、ふぐと濁った呼び方をしますが、下関周辺ではふぐは”不具”で縁起が悪いということで、今でもふくと呼んでいます。
室町時代以降、食べては中毒死する武士が続出し、河豚食禁止令がたびたび出されたものの、やはりその美味さと誘惑には勝てなかったようで、それ以降もこっそりと食べられていたようです。明治時代、伊藤博文が下関でトラフグを食し、その旨さに驚いて河豚食解禁令を出したのは有名な話です。
昔は、天然物しか有りませんでしたが、昭和50年代以降、養殖が盛んになり、最近では中国沿岸でも養殖されています。
ふぐは、他の魚と比べると、鱗と、また人間でいうところのあばら骨、魚では腹骨がありません。表皮は弾力性があって、水を飲み込んで膨れることが出来、また、TTX(テトロドトキシン)と呼ばれる神経毒を餌から摂取して肝臓などに溜め込み、敵に襲われたときに表皮より染み出させて、敵を忌避させます。
なお、トラフグには、輪状筋という組織が目の周りにあり、これがまぶたの役割を果たしています。ゆっくりですが開閉できるんです!(魚で瞼?を閉めれるのはめずらしいんですよ)
主産地
天然物は、日本海南部、黄海、朝鮮半島周辺、瀬戸内海、伊勢湾、遠州灘などで主に漁獲されており、一本釣り、浮き延縄、底延縄、底引き網などで漁獲されます。
最近では、死んでしまうと価値が下がるので、生きたまま持ち帰ることが増えてきたと思われます。その水揚げの多くは高値がつきやすい下関の市場に集まり、全国に出荷されていきます。
養殖物は、長崎県、熊本県、愛媛県を中心に養殖され、活魚車に乗せられて各地に出荷されていきます。関西でも、若狭方面で養殖されていてブランド化を図っているところです。
また、中国でも養殖され、活魚船で日本に搬入されたり、活〆にした後、冷蔵で航空便や、冷凍にされて輸入されていますが、今年は日本の産地価格が安く、メリットが無い為搬入は少ないようです。
選び方
1匹丸ごとのときは、魚体を持ったときに、適度な身の太り具合があるものを選びましょう。生きているものを〆て血抜きをするのですが、失敗すると生臭い身になる為、きちんと処理をしてあるか、確認しないとあとで悲しいことになります。てっさやてっちりで食べると、生臭くて食べられません。
”身欠”と呼ばれる、処理された身になっているものや、てっちりなどに加工してあるものは、身に透明感があって、ぷりぷり感があるものを選びましょう。
身の全体が赤っぽいものは、血抜きが悪いものが多く、また鮮度が低下すると、赤っぽくなったり、身の色が白濁してきます。
料理法、食べ方
身はてっさ(刺身)、てっちり(水炊)、焼き、から揚げなど、淡白な白身なので、どのような料理にも使えます。
また、皮の部分も分解して食べられます。表側の皮は、”みかわ”と呼ばれ、包丁で表面の皮を漉き取ってゼラチン部分だけにして、湯引きなどに、中の皮も”とおとうみ”と呼ばれ、掃除してから、湯引きやてっちりの具材として食べられます。外側の皮がみかわ”三河”、内側の皮がとおとうみ”遠江”と江戸時代の地名をもじってつけられた名前なんですよ。
あと、おすすめは白子(精巣)です。てっちりに入れて良し、焼き白子にしても良し、生の白子に煮えたぎった日本酒をかけて白子酒にしても良し、と濃厚な味が楽しめます。
尚、フグには猛毒が含まれおり、フグを処理(有毒部位の除却)するには免許や資格が必要です。素人による処理は絶対にやめましょう。
協力:尼崎水産物卸協同組合
長谷川水産㈱ 長谷川 幸司
2015年1月の食材【鰤(ぶり)】

説明
出世魚として有名な魚で、縁起物としても扱われ、西日本ではお正月を迎えるために必要な魚の1つでも有ります。
名前の由来は、諸説あり、”師走”に食べるから魚偏をつけて”鰤”とか、賢くて網になかなかかからないからとか、出世魚のゴールで”老魚”、年月を経た魚であることや、脂の多い魚なことから、「あぶら」の「あ」を省略し「ぶり」など、説はいろいろあります。
江戸時代から、”丹後与野の鰤を上品とする”などの記述も残っていて、昔から丹後半島は鰤の本場だったようです。
初ブリ、寒ブリという言葉の通り、水温が下がった時期の魚が一番旨いといわれています。
天然物も漁獲されますが、現在では養殖された魚も多く出回っており、どちらも楽しむことが出来ます。
関西では、つばす>はまち>めじろ>ぶり と大きさごとに名前が変わりますが、関東では、わかし>いなだ>わらさ>ぶりと、ぶり以外は名前が異なります。
年末、せり場にぶりの入った箱がトラックで全国各地から一斉に大量に到着しますが、それが来たら年末商戦もいよいよラストスパート!となります。
主産地
温暖性の回遊魚で、北海道から台湾近辺にまで広く分布し、1~9月頃各地で産卵します。春から夏は北上し、秋から冬にかけては水温の低下とともに南下してきます。太平洋、日本海側ともに生息しており、若魚(もじゃこ~つばす)の時代は沿岸域に定住性がありますが、大きくなると回遊しだします。
天然のぶりは各地で漁獲され、太平洋産はあまり脂乗りのいい魚がいませんが、日本海側は氷見や伊根などのブランドぶりに代表されるように脂の乗ったおいしいぶりが漁獲されます。
養殖ぶりは、主に鹿児島や愛媛で養殖され、そのままの状態で出荷されたり、最近では三枚におろしてフィーレの状態で出荷されます。
選び方
1匹そのままの魚の時は、表面の粘液が透明で、できるだけ鰓の部分がきれいなものを選びましょう。
フィーレの場合は、3枚におろして、鱗も除去してある場合が多いので、身の色が薄い肌色でつやがあるものがいいでしょう。
養殖物と違い、天然物は脂の乗り具合で、身の色が大幅に変わってきます。
脂が乗っていると、筋肉の部分は薄い肌色ですが、脂がないと、筋肉の部分は赤みがかったやや透明な身になります。
身の味は、天然物の方が、旨味成分が多く、美味です。もし天然物(できたら日本海側のもの)があれば、それを狙ってみて下さい!
料理法、食べ方
料理法は意外と限られていて、刺身、しゃぶしゃぶ、照り焼き、塩焼き、大根などとの煮物、あとは雑煮の具材といったところでしょう。
脂も最初は旨いのですが、食べ飽きてきたらしつこく感じてくるので、最初は刺身、そのあとしゃぶしゃぶ、照り焼き・・・と最初に脂の乗りを楽しんで、その後、脂を落とす調理法で食べると、長く楽しめると思います。
ポン酢や大根おろし、マヨネーズなど薬味にもひねりを加えると、おいしく楽しめます。
協力:尼崎水産物卸協同組合
(株)角倉商店 角倉 克彦