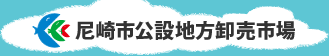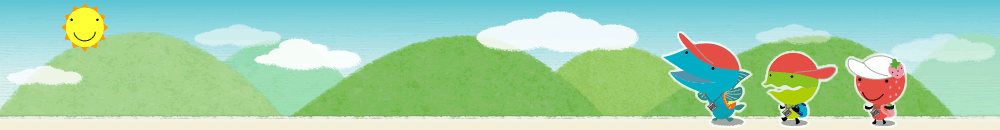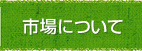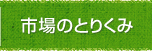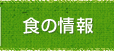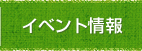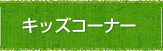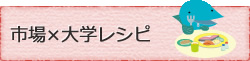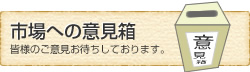2015年2月の食材
2015年2月の食材【牡蠣(かき)】

冬になると店頭に並びだす牡蠣ですが、これは冬から春に旬を迎える真牡蠣です。一般的に牡蠣と言えばこの種を指します。
もうひとつは、夏が旬の岩牡蠣で、昔は痛みやすいため産地でしか食べれない貴重品でしたが、最近では物流の進歩で消費地でも食べられるようになりました。
真牡蠣は、貝類では珍しくほとんどが養殖物で、天然物はごく少数となっています。
戦後、アメリカやヨーロッパで養殖されていた牡蠣が、ウイルスが原因の病気で一気に全滅する事件があり、その際日本の真牡蠣の種苗が提供され、今でもその子孫が世界各地で養殖されています。ヨーロッパなどでよく"オイスターバー"などで提供される牡蠣は、真牡蠣が主流だそうです。
3・11の津波の後、壊滅した三陸の牡蠣養殖業者に、フランスなどの海外の業者が資材などを提供して、昔の支援の恩返しをしたという話もありました。
海外では英語で「R」がつく月が旨いといいますが、日本では「R」が最後に付く9~12月よりかは、真ん中に"R"がつく3月ごろが、風味も身の大きさも一番いい時期といわれています。
「花見過ぎたら牡蠣食うな」「Rの付かない月(5~8月)は食べるな」と昔から言われていて、真牡蠣の産卵期である5月から6月頃にかけて身が細り旨くなくなることが理由に挙げられます。
また、牡蠣は他の二枚貝と異なり岩などに一度付着すると移動しないため、貝柱や足のが小さく、内臓の占める割合が多いため、栄養価が高いことでも知られてます。シーザーやナポレオンなど、英雄に愛された食品でもあります。
主産地
北海道を除く日本各地に生息しています。陸奥湾から九州、朝鮮半島、中国沿岸。種苗を輸出した関係でフランス、アメリカ、オーストラリアなどでも養殖されています。
河川が流れ込む塩分濃度の低い海域の方が生育が良く、現在の養殖方法である垂下式といわれるイカダから吊るして養殖するには、波やうねりの少ない内湾やリアス式海岸が
適している為、瀬戸内海沿岸では川の多い広島、岡山、兵庫と、リアス式海岸の多い宮城、岩手が主産地となっています。
また、海外では韓国でも多く養殖されていて、日本、韓国が約25万トンずつの生産量を誇り、世界の生産量約100万トンの約半分を占めている時期もありました。
当市場では、時期の最初は東北から、その後瀬戸内各地からの入荷となっています。
選び方
殻付のものも、剥き身のものも、漁獲日、加工日を確認して、新鮮なものを選びましょう。
また、殻付のものは、同じサイズのもので持ってみて比較して重たいものを、剥き身のものはできたら、海水に漬かってない無水牡蠣として売られているものの方が、値段は高めですが味は濃厚な傾向があります。
生食用と加工用の違いは、鮮度は同じですが、生食用は滅菌の為、浄水でより洗浄したり、滅菌海水に24時間程度漬けてから殻を剥いて出荷するのが違いです。
産地では、養殖海域の水質定期検査を行い、検査状況に応じて生食用から加熱用に変更したりして出荷しています。
料理法、食べ方
殻付の真牡蠣は、剥いて刺身で食べたり、殻付きのまま蒸したり、焼いたりして食べてもおいしいです。
剥き身のものは、生食用だと酢牡蠣などに、加熱用だとフライ、どて焼き、雑炊、鍋、グラタン、などなどさまざまな料理に使えます。
加熱時は、しっかりと火を通して食べるのは基本なのですが、加熱しすぎると美味しくないので、火が通ったらさっと食べましょう。
あと、栄養価が高い反面、食中毒も起きやすいのが牡蠣の特徴かもしれません。ウイルス性のSRSV(小型球形ウイルス)が原因のものが多く、体調が悪かったり、疲れていたり、一度に大量に食べたりすると、通称「かき中毒」といわれる食中毒を発症することがあります。
2015年2月の食材【青柳(あおやぎ)】

関西では、正式名称の「青柳(あおやぎ)」よりも、「バカガイ」といったほうが分かりやすいでしょうか?
関西では、これからボイルした剥き身が出回り始め、それを見たら、そろそろ春が来るのかなと考えたりします。
剥き身は、そのままボイルしたり、身は生のまま寿司ネタに、貝柱は小柱として天婦羅のネタとして江戸前では有名な食材のひとつです。
また、生のものを伸ばしながら干物にした物も少量作られていて、姫貝(ひめがい)と関西では呼ばれています。
江戸前では、水管に竹串を刺して干したものを「目刺し"(めざし)」、身を開いて干したものを「生干し」と呼ばれ、どちらも、炭火などであぶって食べるととても美味なのですが、製造方法がとても難しく、近年では作る人が減っているそうです。
名前の由来は、場替えという海の満ち引きの砂地の変化に敏感に反応し、一夜で居場所を替えてしまうので「場替」。それが訛りそのように呼ばれるようになったという説と、漁獲して置いておくと足の部分がだら~んとだらしなく貝の外に伸びてきて、その様子が"ばかなようだ"というのが由来という説があります。
主産地
サハリン、オホーツク海から九州、中国沿岸に生息しています。
主産地としては、東京湾の千葉県側、伊勢湾の愛知県、三重県、北海道などが主な産地です。
漁獲方法としては、昔ながらの干潮になったら干潟に出て行って、砂を掘って漁獲する手掘りと、水中にホースを突っ込み、海底の砂と貝を一緒にポンプで吸い上げて、船上で選別して漁獲する通称バキュームという方法、「マンガ」と呼ばれる漁具を船で引っ張り、底引き網のように漁獲する方法の3通りが主流のようです。
選び方
生きている貝は、大きくて持ったときに重く、身がぷりぷりなものがおすすめです。
尚、貝殻は貝類の中でも弱いほうで、取扱は気をつけましょう。
生の剥き身の場合は、身が盛り上がっている、色が鮮やかでくすんでいないものを。冬場はともかく、暖かくなってくると貝類は特に痛むのが早いので注意が必要です。
ボイルの剥き身も、身がぷりぷりしていて、色がくすんでいないものを選びましょう。
あと、剥き身のボイルの場合、バキュームで漁獲されたものは、吸い上げるときに身に砂などが刺さっていて、じゃりじゃりいう時が稀にあります。出来たら手掘りのものを選べるとベストです。
料理法、食べ方
生きているものは、身を開いて軽く湯がいてから、刺身、寿司ネタにしましょう。
貝柱(小柱)も、身と一緒に刺身で提供したり、かき揚げの具材や、天婦羅のネタとしてもおいしいです。
ボイルされた剥き身は、わけぎなどと酢味噌で和え物にしたりするのが一般的です。