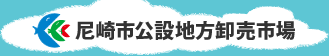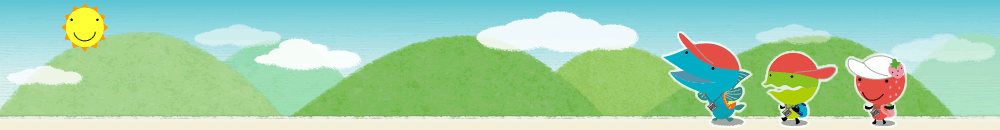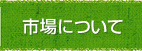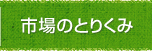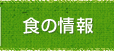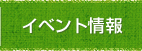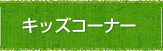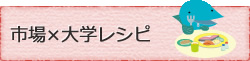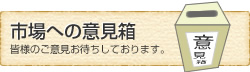2015年3月の食材
2015年3月の食材【浅利(あさり)】

説明
食卓でおなじみの貝といえば、この浅利ではないでしょうか?戦後の高度成長期に埋め立てが進み沿岸では殆どの砂浜が護岸に整備され、住処の浅瀬や干潟がなくなり、馴染みがなくなりつつあるのが残念です。
名前の由来は、浅いところにいる貝とか、海辺で手軽に獲れることから、「漁る」が「漁り」、「浅利」と変化したなど、諸説あるようですが、昔は近くの砂浜を干潮時に掘ればその辺りにいる貝だったようです。
漁獲方法としては、昔ながらの干潮になったら干潟に出て行って、砂を掘って漁獲する「手掘り」と、水中にホースを突っ込み、海底の砂と貝を一緒にポンプで吸い上げて、船上で選別して漁獲する通称「バキューム」という方法、また、マンガなどの金具をつけた漁具を船で引っ張る「底引き」のように漁獲する方法の3通りが主流のようです。
最近では、韓国や中国からの輸入品が多く、国産品は少なくなっているようですが、これから5月ぐらいまでが旬の時期になりますので是非、味わってください。また、潮干狩りに出かけてみて、貝掘りと食べるのを両方楽しむのもいいかと思われます。
主産地
オホーツク海から中国沿岸や朝鮮半島、日本近海では北海道南部から九州に生息しています。
主産地としては、東京湾の千葉県側、愛知の伊勢湾、三重県、北海道などがおもなところです。
選び方
生きている貝は、大きめのもので、比べてみて重たいものがおすすめです。
生きている場合は、砂抜きをしているかを聞いて、砂抜きが出来てないようでしたら、自宅で砂抜きをしましょう。
砂抜きは、ボウルに3%の塩水を作り、その中に浅利を浸して、冷暗所においておきます。最低2時間以上置いておけば砂を吐きます。
生きている貝を保存するときは、塩水を切って、ラップをかけて乾かないようにして冷蔵庫に入れておくと、2日ぐらいは保存できます。
料理法、食べ方
味噌汁、すまし汁、炊き込みご飯、酒蒸し、クラムチャウダーなど。いろいろな料理に使えます。
味噌汁に入れるときは、普通は、火にかける前に入れると思いますが、沸騰してから入れると、出汁は出にくいものの、身はふっくらとして、柔らかい浅利が楽しめます。
冷凍の剥き身(ほとんどが輸入品ですが)もありますが、出来たら生きている殻付を選んで食べてみてください。
食べたときの満足感が違いますよ!
2015年3月の食材【玉筋魚、小女子(いかなご)】

説明
明石周辺などをこの時期車で走っていると、イカナゴを炊く甘い香りがそこかしこから漂ってきます。その匂いをかぐといよいよ春本番というところでしょうか? 地元民でないと、なぜ、生姜やザラメや水あめがスーパーに積んであるのか、最初は理由が分かりませんでした。
本格的にイカナゴが出回りだすと、奥様方がイカナゴを炊く為、他の魚が売れない…それほど夢中にさせる魚でもあります。
昨年の12月から今年の3月頃に産卵してふ化した稚魚が「新子(しんこ)」、2年、3年経過した親魚が「古背(ふるせ)」と呼び名が変わる魚で、鮮度が急激に落ちる為、通常は漁獲後すぐに浜でボイルしたシンコやそれを干したもの、また、ボイルしたフルセが流通の主流です。
釘煮の時期のシンコ漁は、漁船2隻で袋状の網を潮目に沿って広げ、ゆっくりと引っ張って魚を集め、2隻とは違う船で魚を水揚げし、氷で冷やしながら25kgずつ籠に入れます。漁獲後すぐに持ち帰ってせりを行い、その後すぐに仕分けされ、各店頭にシンコ専用のトラック便で配送され、水揚げ後2、3時間後には店頭に並んでいます。また、ボイル加工する魚や釘煮加工する業者も港のせりで購入後、すぐに加工を行い、当日中にボイル品として出荷されます。ここまで特別扱いされる魚は他にはいません。
人間の食料としても重要なイカナゴですが、魚類の食物としても重要で、また養殖の餌としても活用される重要な魚でもあります。
水温が18℃以上になる夏場は砂の中にもぐって夏眠(夏の間休眠)し、水温が18℃以下になると砂から出てきて餌を捕り出すという不思議な習性があります。
今年は漁獲量が少ないという水産試験場の残念な予想が出ていますが、2月26日より大阪湾でシンコが解禁されますので、美味しいイカナゴ、シンコもフルセも食べてみてください!
主産地
日本各地の浅い海に分布し、海底が砂や砂礫の水域に住んでいます。兵庫県ですと大阪湾から播磨灘に多く生息しています。
瀬戸内海各地でも漁獲されますが、水温の関係で、大阪湾周辺から漁獲が始まり、最後は水温が上がるのが一番遅い広島県周辺の漁で終わります。
選び方
シンコは鮮度が命。釘煮にする生のシンコは透明感のある魚体を選びましょう。また、時間がたつとどうしても鮮度は低下します。9時頃~12時頃の店頭着が多いと思いますので、出来るだけ午前中に購入して炊いておくと、鮮度不良で曲がらない釘煮にはならないかと。
釜揚げ(ボイル)のシンコも、鮮度が一番。時間が経つと表面が乾いてきたり、だんだん黄ばんできますので、表面に光沢のあるみずみずしいものが良いでしょう。また、ボイルしたシンコのおなかが赤いものが有りますが、これは餌のプランクトンの色で、赤いほうが美味しいといわれています。
フルセも、鮮度が一番。生は魚の表面に透明感のあるものを。ボイルは、シンコと同じく、乾燥していないものが鮮度が良いと思われます。
料理法、食べ方
生のシンコは、釘煮にすると、長い期間楽しめます。失敗しないコツは、
① 砂糖は必ずザラメを使うこと
② プロが作るようにするには最後に水あめなどを使ってたれを魚に絡ませて、乾かないようにすること
③ たれを沸騰させて、イカナゴを投入するときに、火力全開で少しずつ投入し、たれの温度を下げないこと
がコツだそうです。生姜や山椒、ゆずやレモンなど、いろいろ混ぜ物で風味を楽しめますので、ぜひ試してみてください。
ボイルのシンコは、大根おろしを添えて、ポン酢で食べるのがベストです。炊き立てのご飯の上に乗せて食べるのも美味しいです。
また、かき揚げや卵とじなど料理方法はいろいろありますが、ボイルも生も鮮度が大事です。すばやく食べましょう。
フルセも、生は佃煮やから揚げなどにできますし、ボイルしたものも、そのまま食べたり、あぶってから食べるとさらに美味しく食べられます。また丸干しのフルセも焼くといいですよ。